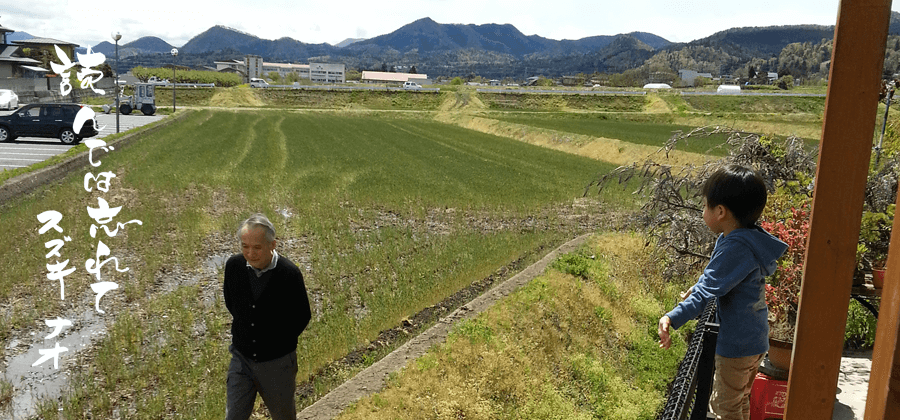『いかれころ』というタイトルがどういう意味なのかわからず読み始めた。主人公の「私(奈々子)」は4歳の女の子で、「コロ」とも呼ばれるくじらの脂が苦手らしいことが冒頭でわかるから、その「コロ」なのかと思ってしばらく読んでいた。しかし「いかれころ」とは、大阪の河内弁で「踏んだり蹴ったり」を意味する言葉だ。
『いかれころ』というタイトルがどういう意味なのかわからず読み始めた。主人公の「私(奈々子)」は4歳の女の子で、「コロ」とも呼ばれるくじらの脂が苦手らしいことが冒頭でわかるから、その「コロ」なのかと思ってしばらく読んでいた。しかし「いかれころ」とは、大阪の河内弁で「踏んだり蹴ったり」を意味する言葉だ。
1980年代、大阪の南部の南河内エリアがこの小説の舞台で、「私」は母・久美子と久美子の家に養子にきた父・隆志の間に生まれた。「私」のいる一家が「分家」で、久美子の実家である「本家」が、頑張れば自転車で行けるぐらいの距離にある。
久美子に連れられて私が頻繁に訪れる「本家」には、久美子の両親(つまり「私」の祖父母)がおり、久美子の妹と弟(「私」の叔母と叔父)がおり、久美子の祖母(「私」の曾祖母)がいて、近くには久美子の母の兄夫妻(「私」の伯祖父、伯祖母)まで住んでいる。関係性をメモして読み進めていかないと私の頭の中は混乱した。たくさんの大人たちが「私」の前に現れ、それぞれの立場からぶつかり合ったり、時になれ合ったりしている。それを4歳の「私」がじっと見ている。
母・久美子の妹である志保子は「私」を子ども扱いせずに優しく接してくれて、この小説の中で「私」が最も心を許しているように見えるのは志保子だ。志保子はかつて精神的な病におかされ、それ以来、一族の中で蔑まれている。「セイシン、セイシン」と大人たちが志保子のことについて揶揄する意味が、4歳の「私」には完全に分かっているわけではないが、そこに何か差別的な意味合いがあることはしっかり感じている。「私」の母である久美子は、志保子を一族の恥のように感じ、ひどく攻撃的に接している。
その志保子に縁談がある。それがこの小説の中心的な出来事で、縁談をめぐって親族たちに慌ただしい動きが生まれ、メンツや立場にこだわる泥臭いやり取りが「私」の目にどんどん露骨に見えてくる。一族の中で、“普通”でない者の立場はどこまでも弱い。いっぱしの男だったら定職に就いて家計を支え、女だったら若いうちにさっさと嫁ぎ先を見つけて子どもを産んで、といった“普通”から少しでも逸れてしまえば、大人たちの中では“傷モノ”扱いだ。
酔うたびに学生運動に夢中だった過去を栄光の記憶として回想する「私」の父・隆志は出世の見込みのない婿養子というだけで親族の中ではほとんど相手にされない存在になっているし、「私」の叔父・幸明は親から期待された真っ当な道を外れ、パチンコに入れあげてふらふらしているからすっかり諦められた人となっている。その父も叔父も、「私」とのやり取りだけを見れば人間味のある人物に見えるし、そういった人物に平然と差別意識を向ける親族たちもまた、一人一人が極端な悪人に見えるわけでもない。
ただただ、当たり前のように差別意識や選民意識が横たわっていて、河内弁で交わされる会話の端々にその意識が顔を出し、もったりとした息苦しさが漂う。しかし息苦しくても、みんなこの土地にいて、抜け出したくても抜け出せない、ぬるま湯のような依存関係があり、それが心地よさげに映る場面もある。小説がただ重苦しいトーンに染まらず、時おり風が通っていくように感じるのは、「私」が決して大人たちを断罪しようとはせずにつぶさに見続けているせいもあるかもしれない(ちなみに小説の中の「私」は4歳だが、数十年後の「私」から語られる情景も入り混じっていて、その時間の行き来も面白い)。
志保子に対して暴力的な言葉を吐きつける「私」の母・久美子ですら、そのようにしか生きられない大人として、「私」から許しの眼差しで眺められているように見える。たとえばもし「私」の友達が「私」に向かって「奈々子ちゃんのお母さんは良いお母さんだね」と言ったなら「私」は「そんなことないわ」と吐き捨てるだろうし、逆に「奈々子ちゃんのお母さんはひどいよね」と言われれば「そうでもないわ」と返すのではないかと想像した。
この小説を読むと、人が人と長く一緒にいることの難しさに打ちひしがれる。家族、親族の終わりの見えないもつれあいにうんざりしつつ、でもその複雑さにどうしても惹かれてしまう。そして「ほんま私は、いかれころや」という久美子の言葉が自分の体に入り込み、今では私の口ぐせのようになってしまった。いかれころや。しかし、かといって自分も自分を取り巻く人々も捨てることはできない。

ここしばらく、NHKがアメリカのABCという放送局と共同で制作して1995年~1996年に放送した『映像の世紀』というドキュメントシリーズが再放送されたのを録画して連日見ていた。
「NHKアーカイブス」というWEBページに掲載された番組の紹介文はこうだ。
20世紀は人類が初めて歴史を「動く映像」として見ることのできた最初の世紀である。映像は20世紀をいかに記録してきたのか。世界中に保存されている映像記録を発掘、収集、そして再構成した画期的なドキュメンタリー・シリーズ。活字とはひと味違った、映像ならではの迫力と臨場感あふれる映像で、20世紀の人類社会を鮮やかに浮き彫りにする。
20世紀は最新の科学技術がリアルタイムで戦争に活用されることにより、人間の暴力性に歯止めがきかなくなっていった100年に見え、第二次世界大戦後も憎悪の連鎖が途切れずに今の紛争にまでずっとつながっているのがわかる。
私はとにかく集団が怖くて、駅の階段で上から降りる人たちの集団が進んでくるのを見るだけで逃げ出したくなるのだが、人間が他人に対して圧倒的な暴力をふるうためには相手を一人として見ず、「〇〇人」だとか「〇〇派」だとか、集団として見ることが必要になる。だからその暴力性を少しでも遠ざけるために普段から集団として見る/見られることに敏感でなければならないと私は思う。
戦争が始まったら私が私であることがめちゃくちゃ簡単にはく奪される。アウシュビッツの収容所で虐殺された人々の死体がブルドーザーで片隅に寄せていかれるのを見ていると、もしかしたら私だったかもしれない人たちの枯れ枝のような体と、今生きている自分の内面との折り合いがつかなくなっていく。
とはいえ、世界で起きている現象を俯瞰して分析しようと思ったら人を集団として見なければ始まらないだろう。結局私たちはその間を行ったり来たりするほかない。そして一人一人と集団の間にある空白を埋めることができるのがこの『いかれころ』のような小説だと思った。
『いかれころ』通販ページ
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス

(X/tumblr)
1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。
スズキナオ最新刊『家から5分の旅館に泊まる』発売中!
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『「それから」の大阪』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『
遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『酒ともやしと横になる私』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス
「酒の穴」新刊『酩酊対話集 酒の穴エクストラプレーン』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
バックナンバー