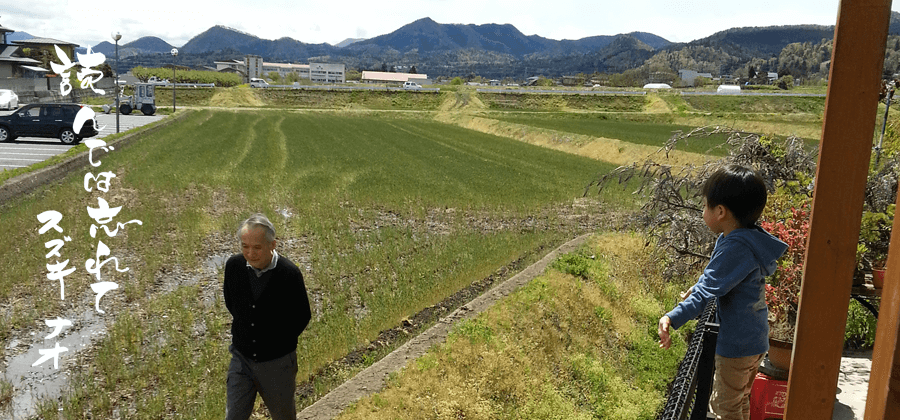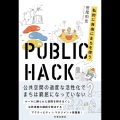手に入れられるものは絶対に全部読むことにしている保坂和志の新刊が出た。それだけで心がざわめく。
手に入れられるものは絶対に全部読むことにしている保坂和志の新刊が出た。それだけで心がざわめく。
『読書実録』というタイトルで、読書日記のようなもの、書評集とか、そういう風なイメージがまずは浮かぶけど、そうではない。
誰かが過去に書き残した本、その中の文章を思考の発火点にしながらも、そこから先はもう自由。別に書評じゃないのだから、最終的にその本の魅力を説明するものになっていなくたっていい。例えば普段自分が本を読んで、色々考えて、「あの本に書いてあったあれとも通じるな」とか、今まで読んだ別の本や、「友達があんなこと言ってたのにも近い」と、本だけでなく自分が見聞きしたあれこれを手あたり次第材料にして考えていく、という、読書がもたらす思考の軌跡を定着させたような一冊、という感じだ。
読み始めて、すごいと思った部分に何かを挟んで印をつけておこうと、机に置いてあったマンションの断水かなんかのお知らせの紙を少しずつ、端から切って挟んでいったのだが、そういう箇所がどんどん出てきて、紙がどんどん小さくなり、最終的に大事なお知らせの内容がなんなのかわからなくなってしまった。
まず、読み始めると一番最初の方に、詩人の吉増剛造が筆写をしているという話が出てくる。筆写、つまり文章をひたすら書き写す。吉本隆明の大著とかをとにかく全部書き写していく。それは写経に近い、信仰に近い行為らしい。らしいというか、私もたまにブログに読んだ本の印象に残った部分を書き写すことがあるのだが、あれは結構大変だ。「今、〇〇というアプリを使えば、スマホでページを撮影したのを自動で文字に変換してくれるよ」と、親切な人が教えてくれそうな気がするけど(それを使うべきな状況もあるだろうけど)、文章を読んで、一度頭の中に溜めて置いて、それを書き、ちゃんと元の文章と合っているか確かめて、という地道な作業をしていると、その文章を書いた人のリズムがゆっくりと体に流れ込んでくるような気がする。
音楽をやる人が、尊敬する人の作った曲を正確にコピーしようとしたら、きっと、その作者がその曲を作った瞬間に近づいたような喜びがあるだろう。曲の展開、運動性を体で味わう楽しみ。私は楽器がまるでできないから想像で言っているけど、違うだろうか。
とにかく、筆写するということはすでに書かれた言葉を自分の体に通すような行為で、この『読書実録』という本自体がまさに、そうやってすでに書かれた言葉が保坂和志の体を通って、また別の形になっていくようなものに見える。

保坂和志がこれまで何度も書いたり話したりしてきた小島信夫という作家についても、やはりこの本の中に何回も出てくるのだが、第2章の「スラム篇」には、その小島信夫と交わした言葉が書かれていて、「評論と違って小説は確信を殺(そ)ぐような表現形式だから、確信に基づく言葉は全部ピントがズレるんですよ」と、小島信夫が言う。確信なんて誰が考えても大事そうなものがかえってピントをズレさせるなんて、最高に面白いな。確信という言葉がこんなに無効化されている場所が今、あるだろうか、どこの世界でも、スポーツ選手でも政治家でも「確信」と強く誇らしげに言う、小説はその確信を「殺ぐ」のか。めちゃくちゃかっこいい。
っていう小島信夫の言葉なのだけど、本当に小島信夫がその通り言ったかどうかはわからない。小島信夫は2006年に亡くなっているのだが、この本の中では、自分が死んでいることも分かっている存在として生きていて、普通に保坂和志と対話している。
なんだよそれ!という話だが、考えてみれば、私たちは、死んだ人とも、頭の中で日常的に対話している。その人が残した言葉を材料に、実際には言わなかった言葉も、その人ならきっとそう言っただろう、と想像する。間違いなくあの人は言っただろう、と思えるのなら、それは言われたのと同じだ。そしてすでにいない人と対話し、自分の考えを前に進めることだってできる。
と、考えると、前述の筆写にしても、この本の軸である、書き残された言葉から出発してどこまでも思考を伸ばしていくようなスタイルも、目の前にいない人との共同作業、という点で共通している。で、そう思うと、待てよ?私たちはみんな、やろうと思えば、死んだ人とも、会ったこともない誰かの書き残した言葉とも協力しあって生きていけるということじゃないか、と、一気に目の前にいない人たちが自分の味方になったような、心強い気持ちがわき起こる。この本を読んでる間中、というか保坂和志の本はどれでも読んでる間中、とにかく強い気持ちが湧いてくる。
それは「自分を信じろ!」とか、「可能性を切り開け!」みたいなそういう強さでは全然ない。むしろそういう強さから一番遠いかもしれない。自分がどこまでもただの媒介になって、そうなることで、現物が至上とされるケチな現実の世界の外にある、もっとラフで、誰がどうしていようと許されるような場所と通じ合えるような。
小川さやかの『「その日ぐらし」の人類学』、酒井隆史の『通天閣』という本が引用され、いい加減に生きることの重要さについて「彼らはひじょうに敏感な嗅覚を持ち、『あ、まずい。こっちに行ったらちゃんとしてしまう、……』と人生の、安定志向の人は気づかない、ひんぱんに出会う岐路で機敏に、ちゃんとしない方を嗅ぎ分けてきた」っていう部分、
ネット上に書かれる暴力的な言葉について「人だかりの向こうから石つぶてを投げてくるようなこういう言葉に出会うと、いまの子どもたちは教室の中でもこういう言葉の石つぶてに常態としてさらされているのかと感じる、まさに酒井隆史が書いた『人間を常態として萎縮させつづけるという統治の技法』だ、みんなそれの片棒を担いでいる、統治の末端の役割を自覚なく日々励行している」と書いている部分、
「私はいま『こうとしか生きられない』と考えない、過去でも書き換え可能と考える。(中略)文字で書かれたものを基準・規範の役に立たせない。文字の前でまったくあらたまらない、みんな少しでもあらたまるから、ブログでもツイッターでも作文でも、基準・規範に貢献している、書くごとに基準・規範が思考の中に育つ、文字によるあらたまった思考は、知らずに体内に巣食う、そのうちに宿主を乗っ取る地球外生物のようなものだ、権力とはそれのことだ」という部分など。
「そんな風にちゃんと会社にも勤めないでいたら将来やばいよ」とか、「日本の経済はこのまま行ったら10年後にはこうなるから、そうなった時、真の地獄が始まるよ」というようなネットでよく見るような、人間は絶対に運命には抗えないみたいな感じの、人間を窮屈にしていく文字の負の力にハッと気づかせてくれる。
本の最後の方にメルヴィルの小説『バートルビー』のことが出てきて、その小説に出てくる「バートルビー」は、頼まれた仕事を拒み続け、何もしないで死んでいくという究極の「何もしないけど存在しているヤツ」なのだが、そのバートルビーが雇われた仕事が、法律文を書き写す「書写人」で、本の冒頭の書写にまた戻っていくのもなんだかすごかった。
『読書実録』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス

(X/tumblr)
1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。
スズキナオ最新刊『家から5分の旅館に泊まる』発売中!
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『「それから」の大阪』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『
遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『酒ともやしと横になる私』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス
「酒の穴」新刊『酩酊対話集 酒の穴エクストラプレーン』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
バックナンバー