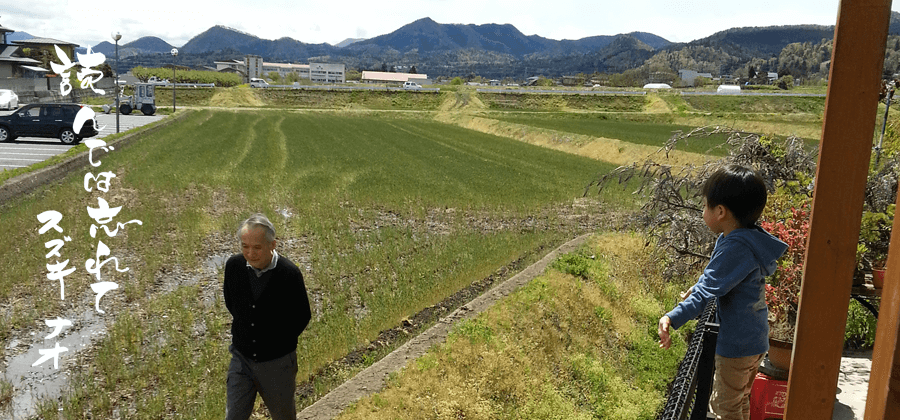著書が日本の離島にある書店をめぐり、お店のこと、そこにいる人のこと、島への旅の模様などを書き綴った本。『離島の本屋』は2013年に出版されていて、その続編にあたる『離島の本屋ふたたび』が2020年の10月に出た。どちらも「ころから」という東京・赤羽にある小さな出版社から出版されている。
この本のもとになっているのは『LOVE書店!』というフリーペーパー上の連載で、その連載は2005年にスタートしたそうなので、そこから数えたら15年という長い月日をかけて作られた2冊の本ということになる(『離島の本屋ふたたび』に収められている文章には『LOVE書店!』誌だけでなく、『DANRO』というWEBサイトに掲載されたものも含まれている)。
北は北海道の礼文島にある「Book愛ランドれぶん」から、南は石垣島の「山田書店 タウンパルやまだ」まで、2冊を通して日本各地の島々の書店が紹介されているが、各章の終わりに添えられる「あの時、その後」と題された再取材コラムでは、その書店が後に閉店したことがわかったり、引き続き営業中ではあっても本が売れなくて苦境に立たされている様子が綴られていたりする。
というか、書店の存続以前に、どの離島もほぼ共通して島民が年々減少している。若い人が島外へ出て行き、高齢者が少しずつ亡くなっていくというその流れは止めようのないものに思える(それでも、一度都会に出て書店で働いていた方が生まれ故郷の離島にUターンして書店を開いたり引き継いだりしたケースが本書にはいくつも紹介されている)。
離島の書店の多くは、書籍以外にも駄菓子を売ったり野菜を売ったり、お茶やお酒が飲めるスペースになっていたりして、多機能的だ。本は売れなくても毎日駄菓子を買っていく子どもがいたり、暇を潰しくるだけの客もいる。どこの島でも、本を買うという行為だけならAmazonをはじめとした通販サービスで済んでしまう時代になって、書店が持つ場としての価値がかえって浮き彫りになっているように思える。
本屋があるということがすでに大きな意味で、住む場所の近くに本屋があり、そこに行けば自分の興味のあるもの、ないもの、どちらにせよ、とにかく何かについて書かれた本がたくさん並んでいる、ということが近くで暮らす人々に何かをもたらしているのではないか、と思う。それが本屋というものなんだから当たり前なのだが、知らないことについて書かれた本がずらっと並んでいるというビジュアルが、実はすごく大事なんじゃないだろうか。
当連載で以前に精神科医の中井久夫さんが“自分の部屋の本棚に本が並び、その背に書かれたタイトルが毎日チラッと目に入る、その瞬間、本の中にある広がりが脳裏をかすめる、それだけで意味がある”っていうようなことをどこかに書いていたと、かなりあいまいな形で引用したのだが、それみたいに、本屋があるということが世界の広がりのイメージになっていることだってあるんじゃないか。

本を手に取って選べるということの意味も大きい。『離島の本屋』に収められたエピソードで、小笠原諸島・父島で書店を営む方がフェリーで年に数回本土に行く機会があると、フェリーが到着する竹芝桟橋からほど近い浜松町の書店に入り、たっぷり時間を使って本を手に取れる喜びを味わうという話があって、普段自分が書店に行こうと思えば行ける環境にあることのありがたみを感じた。
また、書店が一軒も無い沖縄県北大東島で、那覇市内の大型書店「リブロ」が年に1回出張して開催する「出張本屋」の模様をレポートしたページ(こちらも『離島の本屋』に収録されている)では、年に一回、本を手にとって選んで買える機会を子どもたちが心待ちにしている姿が描かれている。ダッシュで会場に飛び込んできて、限られたお小遣いの中でどの本を買おうかと時間をかけて吟味する。
会場の子どもの一人が『離島の本屋』の取材が来ていることを聞いて「へえ、ここ離島だったんだ」と言う場面が描かれているのだが、子どもたちにすれば自分の居場所が「離島」なのか「本土」なのかは知ったこっちゃないというか、選んで生まれてきたわけではなく、ただそこに本屋があったりなかったりする。
鹿児島県喜界島の「ブックス銀座」は、一度は閉店した「銀座書店」を、「島に一軒しかない本屋を守らなくては」と別の経営者が引き継いでリニューアルオープンさせた店。取材中に女子中学生がやってきて『マギ』『東京喰種』といったコミックや東野圭吾の小説を買っていく。「お店がなくなった時はショックで死ぬかと思った。復活して品揃えもよくなって嬉しい!」と彼女たちは語る(この模様は『離島の本屋ふたたび』に収録されている)。
と、そんな風に、島の数少ない書店(あるいは本との関わり)を守り続けようとする人に焦点を当てていく本書だが、随所に著者である朴順梨さんの人間味も感じられる内容になっていて、特に『離島の本屋ふたたび』では、韓国にルーツを持つ朴さんのアイデンティティのことが語られる部分があったり、朴さんが大の“ももクロ”好きで、種子島にある玉井詩織の祖母が営む食堂に立ち寄る模様が割と唐突に描かれたりもする。
また、『離島の本屋ふたたび』の中で朴さんは、必ずしも書店を続けていくことだけが正解なのではなく、時代や価値観にあわせて店の規模を縮小させたり、閉業したりすることだってその人たちなりの正解なのだ、という風に考えるようになる。15年前から始まった連載をまとめたこの2冊は、そのまま朴さんの変化の記録でもあるような気がした。
本を読んでいくとどんどん朴さんに親しみが湧いて、一緒に島の書店めぐりをしている気分か、それは言い過ぎだとしても、「この前行った島の本屋でね」と旅のみやげ話を聞いているような気持ちになる。『離島の本屋ふたたび』のあとがきでは、新型コロナウイルスのことで旅に出られない日々に触れつつも「あと1冊ぐらいは(離島の本屋について)記録しておきたい」と綴っている。さらなる続編をゆっくりと待ちながら、私も早く島に旅がしたいと思う。
『離島の本屋』通販ページ
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス
『離島の本屋ふたたび』通販ページ
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス

(X/tumblr)
1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。
スズキナオ最新刊『家から5分の旅館に泊まる』発売中!
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『「それから」の大阪』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『
遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『酒ともやしと横になる私』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
スズキナオ『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/楽天ブックス
「酒の穴」新刊『酩酊対話集 酒の穴エクストラプレーン』通販サイト
Amazon/e-hon/紀伊國屋書店/シカク(特典つき)/楽天ブックス
バックナンバー