
阪神梅田本店1階の催事場・食祭テラスで2025年8月20日(水)から8月25日(月)にかけて開催される「発酵デザイナー小倉ヒラクの発酵マーケット KOJI/麹」との連動企画として、関西圏で、発酵に関わる仕事をされている三人の方を訪ね、お話を伺った。
お三方がそれぞれ、オリジナリティ溢れるやり方で発酵文化を探求しており、改めて発酵カルチャーの可能性の広がりと奥深さを感じる取材になった。
シリーズの第3回目は、南海電鉄の和歌山市駅近くの舟大工町に「ORYZAE BREWING(オリゼーブルーイング)」というブルワリーを構え、米麹を主原料としたオリジナリティ溢れるビールを作っている木下伸之さんにお話を伺った。麦芽を使わずに米麹でビールを作るという、「そんなことが可能なのだろうか」と思ってしまうような難しい目標に向かって研究を重ね、それを実現させた木下さんの歩みから、その根底にある深い思いを感じられた取材になった。
――今日はよろしくお願いします。木下さんの生い立ちから伺ってもいいでしょうか。
「生い立ちからですか! えーと、この『オリゼーブルーイング』がある場所は、もともと実家のカメラ屋の支店があった場所なんです。うちの実家がカメラ屋で、和歌山市でまあまあ昔からやってて、もう今やってないんですけれども、だから僕はカメラ屋の息子として育ったんです」

南海電鉄・和歌山市駅から徒歩3分程の距離にある「オリゼーブルーイング」
――和歌山育ちなんですね。
「そうです。JR和歌山駅の近くの新内(あろち)っていう、その辺りは昔は三味線の音聞こえてくるような花街だったんですけど。そんな街の方で育ちまして、近畿大学の法学部に進学したんです。で、贅沢に5年かけて卒業してですね(笑)、在学中はずっと軽音楽部にいまして、ひたすら音楽に明け暮れていました」
――楽器を演奏されていたんですか?
「ずっとベースを弾いていました。東京に行って本格的に音楽をやりたいと思っていたんですけど、大学を卒業して、一旦、和歌山のお醤油屋さんに勤めました。そこで配達の作業などをしていたところにお声がかかって、東京で勝負しようと」
――音楽の方でということですよね。
「そうです。吉祥寺をメインに3年ぐらい活動していて、音楽祭でグランプリを受賞したり、FMラジオの番組を持ったり、いいとこまで行ったんですけども、最終的には夢破れてって感じでしたね」
――そうだったんですね。東京で音楽活動をされていたのはおいくつぐらいの時でしたか?
「25歳ぐらいの時ですね、だいぶ前です。もう20何年も前なんで、覚えていないことも多いですけど……まあ自分としては納得できるところまでやって、当時、嫁さんが九州にいたんです。その当時はまだ結婚してなかったんですけど、その縁で、熊本に行きました。醤油屋さんに勤めたことはあったけど、配達の仕事がほとんどで、麹を作ったことはなかったんです。麹を作ってみたいなと思って、味噌屋と日本酒の蔵元に同時に履歴書を出したら味噌屋の方に引っかかったので(笑)、そこで働き始めました」
――なるほど。
「そこで、下働きをしながら2、3年いたのかな。本当に昭和の工場っていう感じの職場で、当時はまだ麹が今のようにもてはやされてなかったので、まさに“3K”の仕事で、3トンぐらいの桶の中に入って味噌の掘り出しの作業をしたり、当時はよく格闘家と間違われました」
――ああ、それぐらいがっしりした体になって。
「そうですね。そういう仕事をしていて、そこが麦味噌と米味噌と甘酒をメインにやってたんですね。そこでの麹作りは、工場なんで、規模が大きいんですね。一回に600㎏ぐらい作って、大きい蒸煮缶をぐるぐる回して、円盤って呼ばれる、人が中に入って麹を作るみたいな機械で作業をしていました。そういう大きな流れだとわからないことか多いので、これはちょっと一から勉強しないといけないなと思って、そこを辞めて、福岡の宗像市というところにある造り酒屋に飛び込みで『就職させてください』と、入らせていただいたんです」
――今度は福岡へ。
「そこで社員として3年ぐらい働かせてもらって。そこは歴史も古くて、創業が寛政何年というようなところで、麹も酒も人の手で作っていたんです。そこで麴作りを勉強させてもらいました。そこで仕事をして、そろそろ結婚をって考えてたのが30歳ぐらいだったかな。それが、福岡独特の風習で、向こうのご両親に『結婚させてください』って言ったら一回断られるっていうのがあるんですよ(笑)」

ご自身の経歴をじっくり語ってくれた木下さん
――えー! そんな風習が。
「今はわからないですけど、僕の時は本当にそうで、『一旦、帰りなさい』みたいに言われて。『一人前になってから来なさい』みたいな。そう言われて、『一人前か。酒蔵だったら、杜氏とか頭にならんとあかんよな。だいぶ先やな』って思ったんです。そしたらちょうどその時に、前にいた味噌屋から『工場長のポジションがあいている。帰ってきてくれないか』と言われたんで、『工場長になったら一人前やろ』と(笑)」
――とにかく一人前にならないと。
「これで結婚できると、熊本に帰ります。工場長として戻って、工場長と言っても、従業員はほとんどいないんで、実質は現場仕事ですね。そこで製造計画とかも任せていただいて、ずっと味噌と甘酒を作る毎日をおくりながら、ゆくゆくは独立しようと、そのためにもノウハウを学ばせてもらって、それで独立したのが11年か12年前でしたね」
――独立されるのと同時に和歌山の方に戻られたんですか。
「そうですね。ここがもう空いていたので、帰ってきて、なんか商売始めようと。っていうのも、味噌屋が非常に、サステナブルじゃないんですよ。1㎏のお味噌が500円でスーパーに並びますよね。卸価格が300円だとして、その人が次にまた味噌を買うのは1か月も2か月も先なわけです。そんなにたくさん消費しないので。で、肉体労働で、単価は上げられないみたいな業態なので、これは無理だろうっていうのを当時から思っていて」
――なるほど。大企業的な規模じゃなければなおさらでしょうね。
「甘酒とか塩麹とか、別の商品で売り上げを確保するというのが主流になっていて、それに代わる何かはないだろうかと。次の何か、もっとサイクルの早いものが欲しいなと思って、甘酒をスポーツドリンクにしようと思ったんですよ」
――スポーツドリンクですか。
「はい。私が独立した当初、2つ商品がありまして、一つは、甘酒をスポーツドリンクにした『ニンジャエナジー』という商品で、ろ過した甘酒をスポーツドリンクとにする、ターゲットとしては、トライアスロンやロードレースをする方を想定していました。ただ、これは鳴かず飛ばずでした」
――なるほど、なかなか認知されなかったんですかね。
「体に負担の少ない補給飲料として、商品自体はすごく好評だったんですけどね。あともう一つが、麴作りのキットだったり、『もろぶた』と呼ばれる麹蓋を作って販売していました。当時、2015年ぐらいですかね、麹蓋って新品が手に入らなかったんですね、中古しかなくて。周りも誰もやってないので、家で麹作れたらいいよねと、自分で大工仕事で、本当にプロ用の麹蓋を作って」
――すごく面白そうですね。
「でも、それも早過ぎたのか、思ったようにはうまく普及しなかったんです。独立当時はそういうようなことをしていました。ちなみに、話が前後するんですけど、麴作りのキットは、今、10年ぶりに改めて作って、受注販売は始めているんです。『オリゼーバケット』という商品名で。よかったら実物があるんで、見てみますか?」
――ぜひぜひ!

麴作りキット「オリゼーバケット」の実物を見せてもらった
「想定しているターゲットは一般の方というよりは、たとえば、麹居酒屋とか、麹料理のお店とか、月に4~5㎏の麹を作りたいとか、そういう需要を満たすものとして、買ってもらおうと。麹作りってプロがいて、一般の方がいたとして、その間の、ホビーで楽しむ方の規模のキットがないんですよ。これは3Dプリンターで自分で設計して作ってるんですけど」
――可愛いカラーリングですね。思ったよりサイズがコンパクトです。

細かいパーツは木下さんが3Dプリンターで作っているという
「完全防水のファンがついているんで、温度管理もお任せで大丈夫という。さらにもう少し小さい家庭用サイズもできないかと研究中なんですけど」
――麴作りが身近になったら面白いですね。
「独立当初の10年前に始めたことではあったんですけど、技術がなかったところを今は3Dプリンターがあるので、自分で細かい部分までできるようになって」
――技術の進歩もあって、よりいいものが手軽に作れるようになったと。
「ホームブリューみたいに、自宅レベルでもっと気軽に色々試して欲しいんですよね。これをやらないと、次の子どもたちの世代からが育たないと思うんです。できたら学校で、みんなで麹を育てて欲しいなっていう(笑)。ちょっと話がだいぶ逸れてしまったんですけど」
――いえいえ。
「こういうことをビール作りの合間にしているんで、大変なんですけどね。えーと、どこまで話しましたっけ」
――独立されて、ニンジャエナジーと麹キットをまずは作ったと。
「そうです。独立して一年目に麹キットを買われたお客様が、『日本にコンブチャ(※「紅茶キノコ」として1970年代の日本でも流行した発酵飲料)がない』という話をされていまして、『やらない?』って。当時、周りでやっている会社は見当たらなかったんです。それでやり始めたんですけど、一応、うちが日本で初めてのコンブチャメーカーらしいんです。で、まさにブルーオーシャンで、それがめちゃくちゃ売れたんですよ」
――へー!
「毎日何十ケースって売って、でも、これは絶対に続かないと思ったんです。これは一過性のブームだと。お客さんからうちにお問い合わせとか来るんですけど、『痩せますか?』ってみんな聞いてくるんです。ダイエット食品みたいな認識で買う方ばかりで、コンブチャは別に痩せる薬ではないので、これは続かないだろうと」
――そういうブームって本当にその時々で移ろいますもんね。
「はい。ただ、おかげで資金繰りには余裕が出たので、これで将来のブルワリーの資金を貯めようと。『ニンジャエナジー』は甘酒をろ過した飲料なんですけど、そこにホップを入れてビールを作りたいというのは設立当初から考えていたことだったんです」

オリゼーブルーイングの醸造施設
――なるほど、いよいよそこにシフトする準備ができたと。
「そうです。その頃から、東京の“ビール塾”に通ってビールを学んだりして、基礎知識として、まず色々なビールを飲みまくるのと、そしてビール作りの知識とが必要なんで、交通費も潤沢に出せるようになったので、毎月のように東京に通って、ということをやっていました。それで、6年前ぐらいですかね、ようやく酒造免許が取れて、それまでは『醸造工房 ferment works(ファーメントワークス)』という屋号だったんですが、2019年に『オリゼーブルーイング』としてスタートできたんです」
――米麹のビール作りがそこから始まったわけですね。
「最初は麦麹のビールを作って、それは今やってないんですけど、ずっと試行錯誤でしたね。よく今でも言われるんですけど、当時作っていたビールを飲んでくれた人にしたら『うーん』っていう味だったと(笑)」
――納得できる味にまでは到達していなかった。
「そこは自分でも認識しながら、でもリリースはし続けないといけない。その頃、辛かったところは、私が文系なんで、あまり化学が詳しくなくて、とにかくずっと実験を繰り返し、繰り返しでやっていくんです。そのスパンがですね、だいたい発酵に3ヶ月ぐらいかかってたんですよ。実験の結果が出るのが3、4ヶ月後みたいな」
――年に数回しかそのサイクルをまわせないという。
「その頃はまだコンブチャがギリギリ売れてくれていたんで、なんとかなっていはいて、なんとなく少しずつ美味しくはなってきていて、でも、やっぱり飲んだお客さんが『ビールじゃない』っておっしゃるんですね。それで一年半ぐらい前に始めたのがライスモルトですね。研究自体はずっと前からしているんですけど。ライスモルトを作れたことでだいぶビールらしくなって」
――ライスモルトというのは作るのにすごくご苦労があったんですか。
「めちゃくちゃ大変でした。ちなみにこれは少し加工したもので、ベースのものとは違うんですけど匂いを嗅いでいただくと、麹の匂いでもないし、お米の匂いでもない独特の感じだと思います」

オリジナルのライスモルトである「オリゼーモルト」を見せていただいた
――本当だ。なんというか、焙煎された感じの香りというか。複雑な香りです。
「こういうのを麹で表現できるようになったということですね。これはちょっとテクニック的にはめっちゃ難しいんで、説明は省きますけど、まあ、ちょっと変わったことをやっていてっていうので、でもこれができてからもずっとブラッシュアップし続けて、飲んでいただいた時に『ちょっと変なクセがあるよね』と言われることもあったんです」
――ビールとして飲んだ時にクセがあったわけですね。
「そうですね。結構私は、作ったものを大胆に変えていく方なんで。ちなみにそういう時は、AIをよく使っていて、AIとずっと喋ってるんです。AIにまず無理難題を投げて、向こうの返しを参考にするんです。うちの弱点として、ホップの香りが乗らなくて、籾臭さのようなものがあったんですよ。それでホップが跳ねないという。ただ、一つだけ黒麹を使ったビールがあるんですけど、それだけ異常にホップの乗りが良くて発酵が早かったんです。黒麴がポイントなんじゃないかと思ったんですが、黒麴はクエン酸を出しちゃうんで、酸っぱくなるしなーと思ってAIに『クエン酸出さない黒麹の作り方はある?』って聞いたら『できますよ!』って(笑)。で、何回か繰り返して、失敗もしたんですけど、できました。だから今はうちではメインが黒麴なんです」
――それが今の最新の味なんですね。
「はい。ある程度そのビールらしさみたいなところまではたどり着けたかなっていうところで。今度は別の業界の方たちが、米麹を使って気軽にビールを作れるようにしていくにはどうしたらいいかというのが課題ですね。どぶろくとは別のアウトプットを作りたいなと。たとえば、香川県の豊島でゲストハウスをされている方がうちのビールを出してくださっているんですけど、海外の方に特にウケがいいと。そこで、自分でもその島の米を使ったブルワリーを作りたいみたいなことで相談を受けたりしています」
――面白い流れですね。
「ただ、難しいところも色々あって、うちも今、ビール事業がやっと黒字になってきたぐらいなんですね。ビール業界って、やっぱりある程度の大きなスケールにならないと儲からないんですよね。うちは実験的なブルワリーですけど、こういうローカルな規模で麹をお酒にするっていうのはかなりリスキーなので、特区制度をうまく使ったりする必要があるのかなとか、色々考えていますね」
――今はハードルが高すぎるわけですね。
「ビールの世界ってこんな風に色々なスタイルに分かれているんですよね。『どんなクラフトビールが好きですか』って聞かれた時に『IPAです』って答える方と『私スタウトが好きです』とか『私はラガーです』とか色々と幅があるんです。私がやりたいのは、この色々あるスタイルを麦芽じゃなくて麹に全部置き換える作業なんですよ」

クラフトビールの系統図を前に説明していただいた
――なるほど。
「それが美味しくできたら、『私はこれが得意』『これが好き』っていうジャパニーズビールのバリエーションができるよなっていうのを想像しながらずっとやってます。そういう色々なバリエーションを提示できたらなっていう作業を6年間やってきたつもりです」
――色々な人が参加できる市場になったら面白いですよね。
「はい。味噌屋もそうなんですけど、醸造業界って夏場が閑散期なんです。甘酒も日本酒も冬場の方が出るんで。それだったら冬場に麹をたくさん作って保存しておいて、それをビールにするとかですね。夏場の閑散期にできる新しい産業にもしていけるんじゃないかと。よかったら『パラレルIPA』を飲んでみますか?」
――え! ありがとうございます!!

オリゼーモルトを使用した「パラレルIPA」
――ラベルが可愛いですね。
「ありがとうございます。浮世絵をベースに、私がデザインしました。これはオリゼーモルトを使ったものです」
――美味しい! コクもしっかりあって、麦を使ってないというのが全然わからないです。華やかな、フルーツっぽい香りもいいですね。
「ありがとうございます。『パラレルIPA』というのは、もし江戸時代からずっと鎖国が続いている平行世界があるとしたら、こんなビールが生まれていたんじゃないかという、うちのコンセプトから名付けたものです」

貯蔵にはワイン樽を使っている。メンテナンスは大変だが、何より安いし、香りがよくなるのだという
――麦芽を使わないビールが主流になっていたかもしれない世界。しかし、こんな風に美味しいビールを麹で作るって、それこそ無理難題なわけですよね。
「うーん、でも最初から麹でやろうというのは決めていますから、自分としてはそこまで大きなジャンプではないつもりなんです。昔、日本酒を作っていた時に、分析作業という仕事があって、もろみをすくってろ過して、発酵具合を確認するんです。その時に飲んだアルコール度数5%ぐらいの日本酒がめっちゃ美味しくて飲みやすかったんです。もともとお酒がそんなに強くないこともあって、アルコールの度数の低い日本酒みたいな麹の味のするものが飲みたいとずっと思ってたんですよ」
――たしかに、日本酒って度数が高くてそんなにたくさん飲めないですもんね。このビールならグイグイと飲めます。それにしても、難しい課題に対して一つずつ学んで形にしていくところに頭が下がります。
「音楽をやっていた時もそうだったんですけど、フロントマンを目指していたわけでもなくて、卓をいじるのが好きだったんです。時代的にちょうどDTMの黎明期で、それを使って曲作りするのがすごく楽しくて、基本的にはそういう裏方思考なんで、じっくり取り組んでいくのが好きなんですよ」
――その成果がこの美味しいビールになっているんですね。ちなみに、オリゼーブルーイングとしては、「発酵デザイナー小倉ヒラクの発酵マーケット KOJI/麹」では何を提供される予定ですか?
「会場のバースペースで生ビールを出す予定です」
――またそこで生ビールを飲めるのを楽しみにしています! 今日はありがとうございました。

木下さん、ありがとうございました!
取材終了後も、「麹作りが身近になったらこんな面白い可能性がある」というお話を、木下さんはたくさん聞かせてくださった。それこそ、麹作りキットを販売しているところからもわかる通り、間口を広げて、多くの方が参入できる仕組みを作ることが木下さんの大きな目標になっているようだった。
それはきっと、あえて利他的に振る舞おうとしているのではなく「単純にその方が楽しいから」という思いがあってのことだろう。その軽やかな身のこなしと、こだわる部分にはどこまでも徹底して追求していく姿が、なんともまばゆく、心強く感じられるのだった。
「オリゼーブルーイング」(HP)
住所:和歌山県和歌山市舟大工町3 きのしたビル1F
営業時間:11~18時
営業日:金曜日・土曜日(飲食店・ビアバーではなく、醸造所に併設された有料試飲カウンターを金・土にオープンする営業形態となっております)
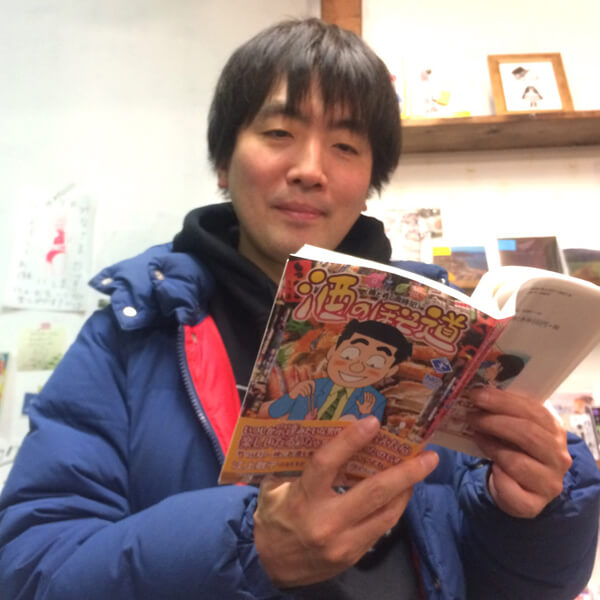
(X/tumblr)
1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。
バックナンバー


