
阪神梅田本店1階の催事場・食祭テラスで2025年8月20日(水)から8月25日(月)にかけて開催される「発酵デザイナー小倉ヒラクの発酵マーケット KOJI/麹」との連動企画として、関西圏で、発酵に関わる仕事をされている三人の方を訪ね、お話を伺った。
お三方がそれぞれ、オリジナリティ溢れるやり方で発酵文化を探求しており、改めて発酵カルチャーの可能性の広がりと奥深さを感じる取材になった。
シリーズの第1回目は、滋賀県の北東部・湖北エリアにある長浜市に拠点を置くクラフトどぶろくの醸造所である「ハッピー太郎醸造所」を訪ね、醸造家の池島幸太郎さんのお話をたっぷりと伺った。
“ハッピー太郎”こと池島幸太郎さんは、3つの日本酒の蔵元で経験を積み、2017年に滋賀県彦根市に麹の専門店を開業。麹の世界を追求した先の発展型として、長浜市の複合商業施設「湖のスコーレ」に拠点を移して現在の業態をスタートしたのが2021年12月のことだった。

「ハッピー太郎醸造所」は「湖のスコーレ」の中にある
ご本人が「話すと長くなります」とおっしゃるその経歴や発酵文化との関わり、また、2021年から取り組んでいるどぶろく作りについてまで、そのお話は多岐にわたる。ちなみに、「ハッピー太郎醸造所」がある「湖のスコーレ」は2021年12月、JR長浜駅から徒歩6分ほどの場所にオープンした施設だ。奈良の人気カフェ・雑貨店「くるみの木」のオーナーである石村由起子さん、「D&DEPARTMENT」の相馬夕輝さんがプロデュースを務め、黒壁スクエアや長浜大手門通り商店街といった長浜の観光スポットからもほど近い中心地にある。まずはその「湖のスコーレ」のことから。
「この『湖のスコーレ』は、400坪ほどの敷地があるんですけど、ワボウ電子の月ケ瀬義雄社長をはじめ、地元の経済人たちが出資してできたものなんです。長浜の街には、自分たちの事業の利益を街づくりに投資するという文化が昔からあるんです。その象徴が、向かいの曳山博物館なんです」

「湖のスコーレ」と目と鼻の先にあるのが「長浜氏曳山博物館」。長浜曳山祭の山車が展示され、その歴史を学ぶことができる
「長浜には、毎年4月に行われる、子ども歌舞伎で有名な曳山祭りというお祭りがありまして、そのお祭りを中心に街の人たちの一年がまわっていると言っても過言じゃないんです。豊臣秀吉の時代からあるといわれる大事なお祭りで、その時期は自分の事業もほったらかしでみんなお祭りに専念します。この祭りをずっと続けていくためには街が元気じゃなくちゃいけないということで、曳山祭りが中心となって、街の方が力を合わせてきました。この曳山博物館も、地元の方々が私たちの文化を未来に残していこうと、お金をかけて作ったのものです」
――「湖のスコーレ」、すごくおしゃれな雰囲気ですね。
「残念ながら街にシャッターが増えつつある中で、新たな客層にアピールしていこうと、その曳山博物館の目の前に建てたのがこの『湖のスコーレ』なんです。天気のいい日は、建物の目の前から向こうに真っすぐ伊吹山が見えるんです。伊吹山は我々にとっての霊山のようなものでして、一晩で10メートルの雪が積もったという記録もあるほど、雪が積もるんですね。それが何十年もかけて地下水となって琵琶湖に流れていきます。伊吹山は石灰岩でできた山なので、長浜の地下水は硬水なんです。硬度が150mgぐらいあります。私の醸造所では、その水を醸造用として、濾過もせず、調整もせずに使わせてもらっています」

「ハッピー太郎醸造所」も自然な木の風合いが感じられる素敵な外観だ
「この、入口近くに吊られている杉玉は奈良のものなんですが、なぜここにあるかというと、奈良の『くるみの木』のオーナー・石村由起子さんがこの『湖のスコーレ』をプロデュースされたからです」

「湖のスコーレ」の入口付近に吊るされた杉玉
「石村さんは企画にあたって、この施設を『滋賀について学べる場所にしていきましょう』と考えて、滋賀のあちこちを取材されたんですね。一緒にこの施設を盛り上げていこうという人を探してまわられて、たまたま僕のもとにも連絡がきたんです。当時、僕は滋賀の発酵文化についてネット上で発信していたんです。その頃は、暇だったんで(笑)」
――当時はまだ長浜にはいらっしゃらなかったんですか?
「はい。当時は彦根にいました。2017年に彦根の方で起業して、麹屋、鮒寿司屋、漬物屋のようなことをやっていました。そこに『湖のスコーレ』の企画チームが来られて、一緒にお話しをする中で、『ハッピーちゃん面白いね、一緒にやりましょうか』ということになって(笑)。もともとはここで販売する滋賀の食品をセレクトする役回りという話しだったんですが、それが発展して、『ハッピーちゃん、ここでどぶろくやりませんか』と、向こうから言っていただいたんですよ」
――そうなんですね! 当時はどぶろくは作っていなかったんですか?
「一切作っていなかったんです。酒造免許もない状態でした。ただ以前から屋号は『ハッピー太郎醸造所』としていて、僕が12年間、日本酒業界で働いてきて、『いつか自分の酒を造りたい』というような夢があったので、醸造所という名前をつけていたんです。ただ、『湖のスコーレ』の企画チームからお声がけいただいた当時は、ご飯が食べられる程度の売り上げにやっとなってきたという時で、しかも、それ以上の売り上げは見込めないなというような時だったので、断るっていう選択肢がまるでなかったですし、即答で『やります』と言わせていただきました」
――なるほど。
「当初は滋賀県内の食品を仕入れてここで販売しようと思っていたのですが、ただ商品を仕入れて販売するお店は都会にいくらでもあるわけです。それでは事業として長続きしないと、『湖のスコーレ』では、ものづくりをしながら販売をしていこうと。このチーズは、滋賀で有名なチーズ職人の古株つや子さんから作り方を教わって、それからは20代の女性を中心にしたメンバーで自力で作っているものです」

「湖のスコーレ」オリジナルのチーズやスイーツが並ぶ一角
「ほとんど素人のような状態から、すごく勉強して、今では賞をとるような、かなりクオリティの高いチーズを作っていらっしゃいます。僕も商品を共同開発していて、『味噌フロマージュ』という商品は、琵琶湖の沖島で作られている味噌を参考にした味噌を使ったものです。また、チーズを作るとホエーがものすごく出るので、それをどぶろく作りにも活用しています」
――無駄がないですね。
「これは滋賀の名物の鮒寿司ですが、鮒寿司には卵を持ったメスの鮒を使います。かつてはオスの鮒もなれずしに使われてきたのですが、時代が変わって、鮒寿司が日常食から高級品になった今、卵を持たないオスの鮒はあまり必要とされていないのが現状なんです。それはあまりにもったいないと考えられたのがこの商品で、オスの鮒のお腹の中にチーズを入れて一緒に発酵させた鮒寿司なんです。「近江佃煮庵 遠久邑」という沖島出身の佃煮屋さんが開発したもので、チーズを、後から詰めるんじゃなくて一緒に発酵させるというのはとても難しく、かなり試行錯誤されたんですが、これは傑作です」

オスの鮒をチーズと一緒に発酵させた商品も
「廃棄されがちな鮒のオスを買い取ってそれを価値のある商品にしていく、それを継続的な事業にできないかと、こういう難しいことにトライしておられるのは、実は琵琶湖があるからなんです。滋賀県が紹介される時、琵琶湖の形のマークがよく使われるんです。滋賀県の形じゃないんですよ(笑)」

琵琶湖の形が滋賀県のシンボルとしてよく使われるという
「あくまで琵琶湖なんです。琵琶湖の面積って滋賀県全体の6分の1ぐらいで、実はそのぐらいの大きさなんですが、でもやはり大きな湖には違いない。その琵琶湖がすごく汚れてしまった時期があったんです。1970年代に赤潮が大発生して、その時に立ち上がったのが地元の主婦の方たちでした。赤潮の原因が、当時よく使われていた合成洗剤にあることがわかって、合成洗剤じゃなく、石けんを使おうと、『琵琶湖の石けん運動』というものが始まるんです。その石けんを作るための原料に使用済の食用油を使おうということになって、油の回収もされるようになりました。そうやって始まった石けん作りは今も続いていて、油自体も環境に配慮したものを作ろうというので生まれたのがこの『菜ばかり』という菜たね油です。地元の無農薬菜種を低温搾油したもので、今はNPO法人として製造されています」

環境に配慮して作られた菜種油「菜ばかり」
「そしてその搾りかすは、米ぬかを加えて発酵させて、東近江市にある政所茶の肥料として使われています。そんな風に、何十年前から循環を考えたものづくりが行われてきたのは、滋賀県に琵琶湖があるからだと思います」
――琵琶湖の存在がそれだけ大きいわけですね。
「このカフェでは色々なメニューを提供しているのですが、『発酵カレー』というメニューがあります」

館内に併設されたカフェの人気メニュー「発酵カレー」
「ちなみに、普段生活をしていて麹を毎月1㎏買ったりしますか?」
――いや、買わないです……。
「そんなに麹を買うということはほとんどありませんよね。僕は2017年に麹屋として起業したんですが、だから、完全に間違ってるんです(笑)。しかも、老舗の麹屋さんならまだ信頼してもらえますけど、ぽっと出の店の麹ってどうなのって(笑)。みなさんそう思ったようで、すごく苦労したんです。売り上げが上がらず、牛乳配達の仕事をしたりとか、大変な日々が続きました。『発酵カレー』はその頃に作ったもので、マルシェのようなイベントに出店した時に、カレーは食べてもらえたんです。そして一緒に少し麹を買ってもらえることもあって、なので当時はとにかくカレーを作っていました。お味噌、甘酒、お味噌用の大豆を蒸して入れています。で、作っていた漬け物をアチャールにして。一日100食は出せるぐらい、ご飯をたっぷり炊いていって、余ったご飯は後で甘酒にして、ロスがないようにして、そんなことをしながら、発酵食品と一般の方をどう結べばいいのかっていうことを勉強していった毎日でした」
――なるほど……ここに至るまでに長い道のりがあったんですね。
「そうなんです。そして、ここでやっと『ハッピー太郎醸造所』の話なんですが(笑)、ここが麴室です」

「ハッピー太郎醸造所」の麴室も、もちろん「湖のスコーレ」の中にある
「クラフトサケの業界も色々ありますけど、うちとしては麴室はしっかり作りたいと、そういう希望を出して、小さな醸造所にしては立派な麴室ができました。ここがうちの心臓部です。僕が麹屋として起業してここに移転するにあたってその発展型として醸造を行うというのが僕のテーマだったからですね。一つ10㎏盛れる麹箱が、6つ置ける広さになっております」

杉を使って作られたという麹室
「実は昔の麹屋さんや昔の酒蔵の麹というものは、麴室に目いっぱい麹を入れて湿度を高めていたんです。熱源は麹そのものの自熱で、その熱だけで保温するというのが昔の麴室の使い方なんです。今は電熱線とか色々ありますけど、その頃はないですから。しかも湿度も高めにして、狭い部屋に目いっぱい麹を持ち込むというのが昔の麹の作り方です」
――勉強になります。
「それが戦後、労働酒としての日本酒でなく、嗜好品としての日本酒作りがさかんになっていく中で、麹をデザインするようになっていきます。いらない味を削ろうという、引き算でお酒が作られていく。そういう場合、味の芳醇な麹って邪魔なんです。そこでどうするかというと、乾燥させて麹を作る。麹菌ってカビですから、乾燥させると成長しづらくなって、水のある方へ根を生やすようになる。周りには繁殖させず、中に入っていく麹を作っていくという、デザインされた麹の考え方が日本酒業界で広まっていきます。一方、味噌作りのための麹って、そうではなく、とにかく大繁殖させるんです」
――そういう違いがあるんですね。
「麹を目いっぱい入れて、湿度の高い状態で作る味噌用の麹でどぶろくを作っているのがうちの特徴です。湿度が高いといっても、水分がぽたぽたと天井から垂れて根腐れするような状態ではまずいんです。そこで木の部屋が必要になってきます。滋賀県の杉を使っているんですが、これが水分を吸ってくれるんです。もしステンレスの部屋だったら天井から雨漏りしているような感じになります。根腐れしないように、でもしっかり保湿しつつ作っていくというのがポイントです」
――そのためにもこの麴室が大切なのですね。
「では、醸造所の中へ入っていただきます。これがうちのフラッグシップ的なお米で、滋賀の『池内農園』で作られている、『滋賀旭』という在来種のお米です。五町の田んぼ、すべて自然農法。三十年間、無肥料無農薬自家採取でやってこられている農園です。すべてのどぶろくにこれを使っているわけではないのですが、このお米に出会って、農家さんのすごさを知りました」

池島幸太郎さんが惚れ込んだという「池内農園」のお米
「見ていただくとわかると思うんですが、自然農法とは思えない美しさです。初めて食べた時に、一粒一粒のお米のパワーがすごくてびっくりしたんです。で、当時の僕は蔵人だったんですけど、ぜひ田んぼを見せて欲しいと遊びに行かせてもらったんです。その頃、趣味で鮒寿司を作っていたんですけど、このお米を使ってみると、香りの傾向が他のお米とは違ったんです」
――鮒寿司の風味もお米の違いでかなり変わってくるわけですね。
「そうなんですよ。僕がどぶろくを作るに当たって考えたのは、どぶろくって、味噌とか鮒寿司と違って水をどんどん入れる発酵ですよね。つまり、よりお米が溶けるんです。水分が多いから発酵が旺盛に進むんですけど、じゃあお米がそれだけ溶けるんであれば、土壌に優しい農法をとっておられる滋賀のお米を使って、それを徹底的に溶かして、美しいどぶろくを作ってみたいと思ったんです。他にも『SHIBATA GROUND MUSIC』で作られている『ありがとう米』や、野洲にある『中道農園』のお米を使っていて、そういう、環境を考えた農家さんが多いのも滋賀のよさだと思っています」

「ありがとう米」の米袋にも琵琶湖のマークがあった
「ここでどぶろくを作っています。麹屋として起業しましたが、個人の麴屋で一人飯を食うくらいなら可能ですが、事業として成長させるには至難の業であることがわかりました。ただ、どぶろく事業を始めますと、お酒には付加価値がつけられますし、エンタメ的な要素があって、生活必需品とはまた違ったものとして提供できて、滋賀という土地を表現するようなものつくりができる。麹屋の発展型として、こういうやり方もあるということを未来に残したいなと、それがどぶろくをメインにしている理由なんです」
――なるほど、麹屋としての経験があったからこそなんですね。
「先ほど説明させていただきましたけど、以前、沖島の味噌を参考にした味噌づくりをしていました。沖島の味噌って『七日味噌』として有名なんです。仕込んでから一週間後には食べ始める。それを参考にして白味噌を作り始めてわかったのは、京都の白味噌屋さんって、街の中の狭い敷地内でぐるぐるまわせるように、早く出せる味噌を作っているんです。それを一年寝かせるとか、八丁味噌みたいに三年寝かせるということになると、土地持ちしかできない。発酵文化って資本主義と相容れない部分もあるんです。でもそこまで時間のかからないものをあえてやって、発酵食品への入口を広げていくのが僕の役割なんだろうなと思って、どぶろくもその文脈にあると考えています」

小さな敷地だが、効率よくどぶろくを作っているという
「本格的な酒の文化を哲学的に掘り下げていくっていうのは日本酒業界の方がやっているので、それに憧れはあったんですが、僕は麴屋さんになりました。麹を販売する中で僕が出会ってきた主婦の方々は、ほぼ日本酒を飲まない方々だったんです。アルコール度数が高いイメージがあって、子育てしている中であんまり酔うわけにはいかないとか、そういう理由が多かった。そういう人たちに向けて、アルコール度数は低めで、少し贅沢な気持ちになれるような一杯を作れないかということが、甘酒の延長にあるようなどぶろくを作る上での目標になりました。そのために必要なのがこの機材です」

保温ジャーも、どぶろく作りに欠かせない大事な道具
「これは保温ジャーなんですけど、炊飯器で甘酒を作る方法があるじゃないですか。その延長線上で、ここで作った甘酒をタンクに入れて、だから『ハッピーどぶろくって甘酒みたいだよね』ってよく言われるんですけど、本当に甘酒を発酵させて飲み良い時に瓶詰をしているっていう感じなんです。日本酒を作りたいけど作れないからどぶろくをっていうのではなく、麹屋さんが発展型として作るどぶろくという、そういう作り方をするようになってきてようやく自分の居場所ができたように感じました」
――お話を伺っていて、これまでに経験してこられたことが全部繋がっているのがわかりました。
「でも、課題は色々あります。ここの冷蔵庫は二坪しかないんです。だからたとえば甘酒を作る用の麹を確保すればするほど、どぶろく用の麹の在庫を入れる場所がなくなってしまう、なので、次の目標としては、ここはどぶろくラボとして使って、どこか他の場所に甘酒の工房を作って、そっちもまわしていけるようにしたいです」

画像キャプション:醸造タンクの中を見せていただけることに
「これは全麹で、蒸米の入ってないものなんですけど、これをスターターにして、たとえばクロモジのどぶろくであれば、クロモジ茶をまず作るんです」

タンクの中にはどぶろく作りの基礎になる麹が収められていた
「甘酒って麹とお湯で発酵させるので、そのお湯のかわりにクロモジ茶を使うわけです。最初は香りが馴染まない感じだったのが、3日ぐらいすると馴染んでくるんです。境界線がだんだん溶けて調和していくんですね。その過程が面白いです。説明はこれぐらいにして、試飲してみますか?」
――やった! ありがとうございます!

「ハッピー太郎醸造所」のどぶろくのラベルには早川鉄兵さんの切り絵があしらわれている
「ちなみにこのラベルは切り絵作家の早川鉄兵さんがデザインしてくれたもので、伊吹山の伝説を絵本にしたりされている方なんです。キツネを描いてもらったのは、キツネはお稲荷さんでもあるし、もぐらをやっつける、田んぼの守り神としての意味もあっていいなと。近くにある『大通寺』には『お花ぎつね』という言い伝えがあるので、そことも繋がるなと。これが『うきうきホップ』です。今のうちの一番人気はこれです」

「ハッピー太郎醸造所」の商品の中でも一番人気だという「うきうきホップ」
――美味しいです! 新しい発見があって、間口の広さも感じますね。なんだかテンションが上がる味で、大勢での飲み会のお土産に絶対喜ばれそうです。
「ありがとうございます。そしてこっちが季節限定の『フレッシュハーブティー』なんですが、広島の『梶谷農園』さんという農家さんのハーブを使っているんです」

ハーブが複雑な味わいを生んでいる「フレッシュハーブティー」
「以前、『ハッピーどぶろく』を知人経由でそこに送ったところ、大量のハーブが送られてきまして(笑)。それをどぶろくにしてみたのがきっかけなんです。表情のあるワインが好きな方にはおすすめかと思います」
――すごく楽しい味! ミントの香りがすーっと爽やかで、いいですね。
「次はお茶のどぶろく『政所の茶縁』です。政所のお茶を使っています」

政所のお茶を使ったどぶろく『政所の茶縁』
「政所には、昔の栽培方法が残っていて、その栽培方法を誇りにされているんです。平番茶っていうお茶があって、硬くなった葉っぱをギュウギュウに詰めて蒸して乾燥させた、生活の中で飲まれてきたお茶なんですけど、この平番茶を仕込み水に使っています」
――お茶の香りがしっかりあって、それでいてどぶろくだというのがなんとも面白いですね。
「そしてこれが最後、『オリエンタルホエー』というどぶろくで、チーズのホエーを活かしたものです」

先ほど説明のあった通り、チーズを作る際に副産物的にできるホエーを使ったどぶろく
「カルダモンなど、スパイスを使っています。チャイとラッシーの中間みたいな味になっています。これはこの施設限定で出しているものです。間口は狭い味かもしれませんが、これが一番好きだという方もいます」
――あー! 確かにちょっと個性的な味に思えますけど、これも美味しい! 私もかなり好きです。ちなみに「発酵デザイナー小倉ヒラクの発酵マーケット KOJI/麹」ではどんなものが飲めるんでしょうか。
「会場内のバーで、クロモジのどぶろくと『うきうきホップ』を提供する予定です。他のフレーバーも購入いただくことができます」
――それは楽しみです。今日はありがとうございました!
ちなみに、この取材の前、長浜の街を散策しつつ、昼食をとれるお店を探していた。「焼き鯖そうめん」が名物だという「翼果楼」に入ってみると、メニューの中に、「ハッピー太郎醸造所」の「ハッピーどぶろく」が! 取材前なので酔い過ぎないように気をつけつつも一杯いただいてみると、鮮やか風味とどぶろくならではの舌触りが楽しく、焼き鯖の味ともすごくよく合った。

長浜の人気店「翼果楼」でも「ハッピー太郎醸造所」の「ハッピーどぶろく」が提供されていた

ちなみに「焼き鯖そうめん」も「焼き鯖寿司」も絶品でした
「ハッピー太郎醸造所」のどぶろくについて、味見させていただく前は、ちょっとクセのある、インパクト重視な味わいなのでは……と、失礼ながら勝手にイメージしていたのだが、どのフレーバーを試飲させてもらってもそれぞれに新鮮な驚きがあり、そうでありながら、他の料理ともどんどん合わせてみたくなるような親しみやすさを感じた。気になる方は、ぜひ一度飲んでみて欲しい。
「ハッピー太郎醸造所」(HP)
住所:滋賀県長浜市元浜町13番29号 湖のスコーレ内
営業時間:11~18時
定休日:日曜日
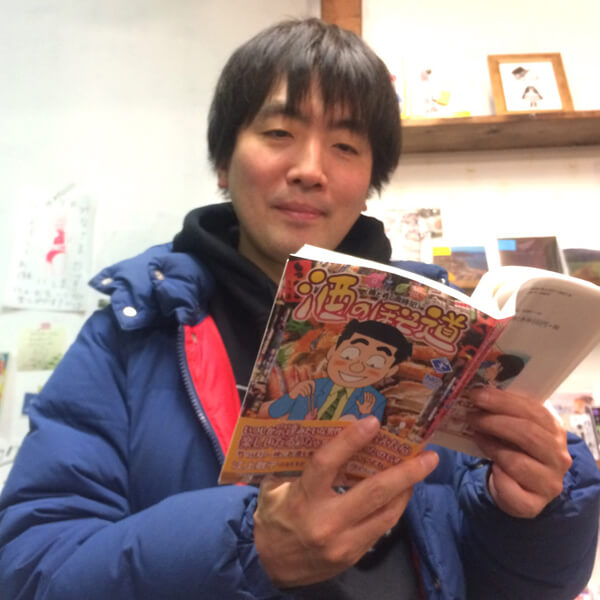
(X/tumblr)
1979年生まれ水瓶座・A型。酒と徘徊が趣味の東京生まれ大阪在住のフリーライター。WEBサイト「デイリーポータルZ」「集英社新書プラス」「メシ通」などで執筆中。テクノラップバンド「チミドロ」のリーダーで、ことさら出版からはbutajiとのユニット「遠い街」のCDと、単行本『ずっとあった店 スナック屋台おふくろ編』を刊行。大阪・西九条のミニコミ書店「シカク」の広報担当も務める。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』『家から5分の旅館に泊まる』(スタンド・ブックス)、『「それから」の大阪』(集英社)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)、『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、『大阪環状線 降りて歩いて飲んでみる』(インセクツ)。パリッコとの共著に『酒の穴』『酒の穴エクストラプレーン』(シカク出版)、『椅子さえあればどこでも酒場 チェアリング入門』(ele-king books)、『“よむ”お酒』(イースト・プレス)、『ご自由にお持ちくださいを見つけるまで家に帰れない一日』(スタンド・ブックス)。
バックナンバー


